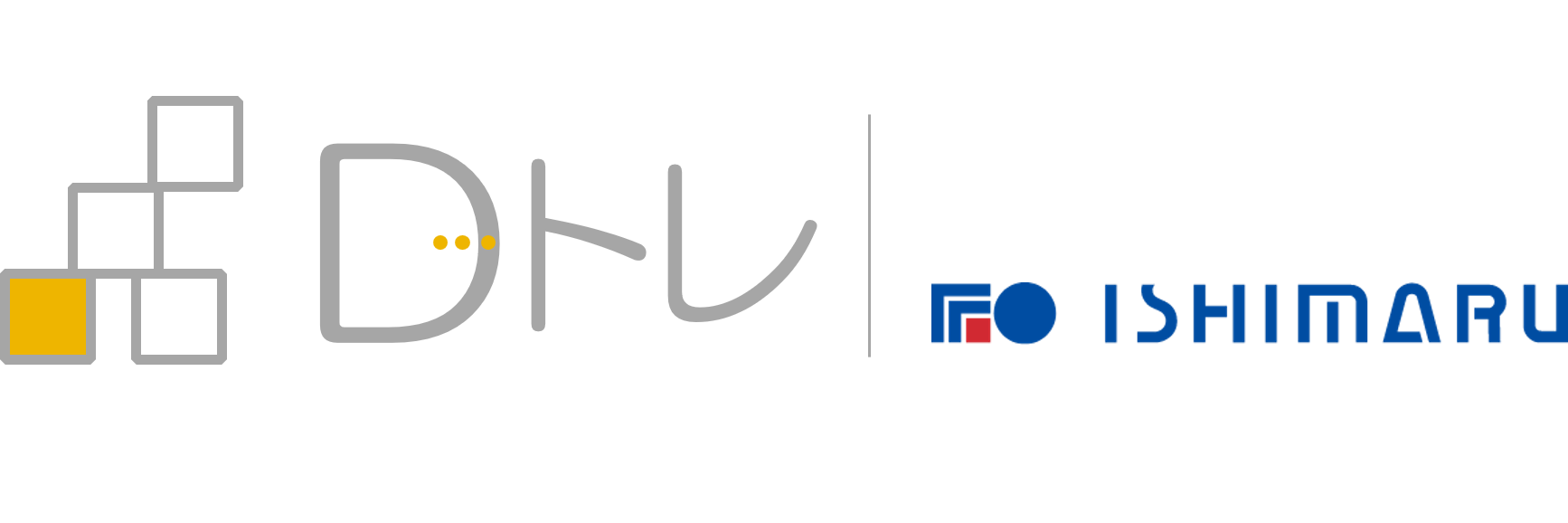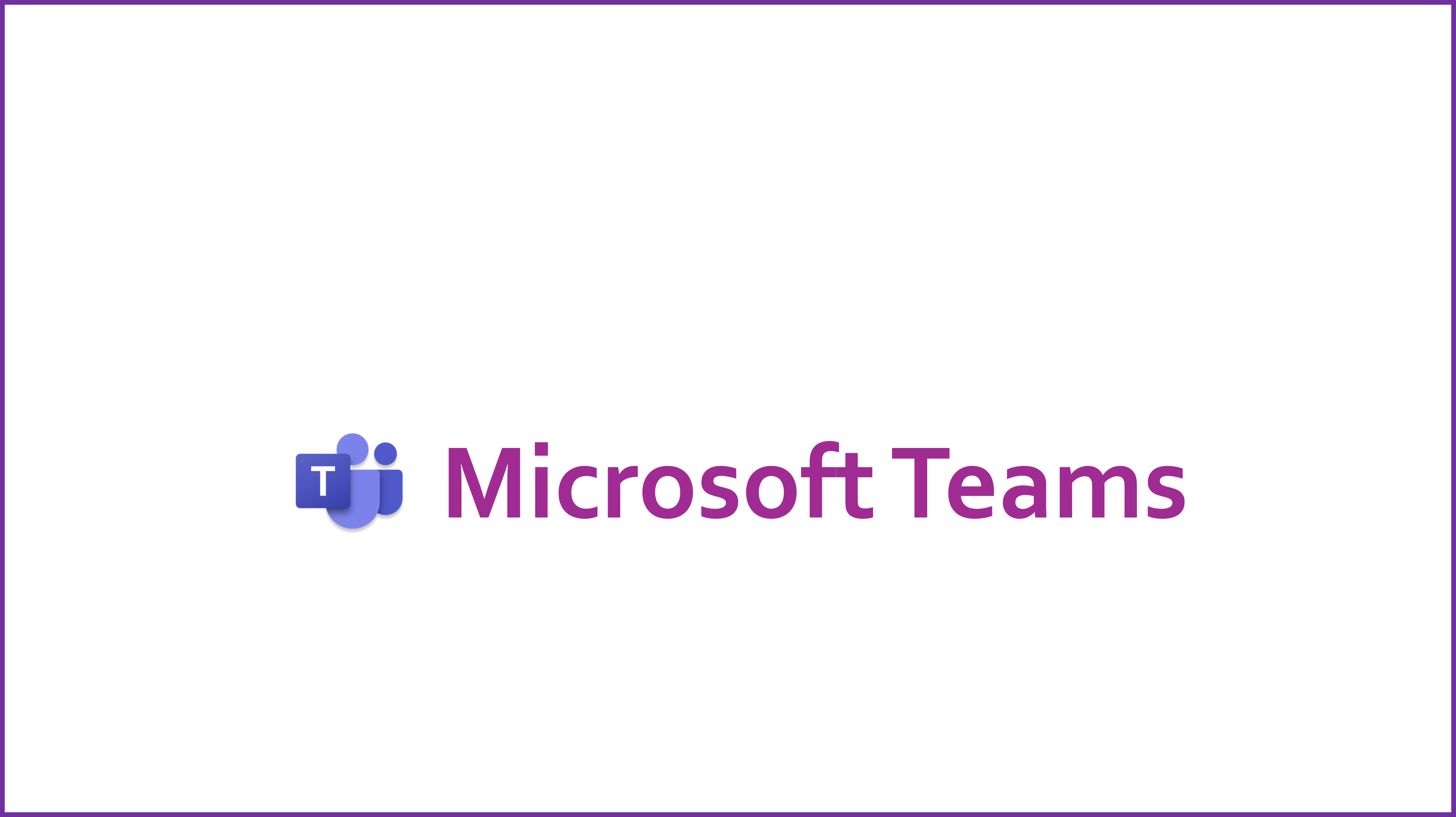セキュリティの新常識!「ゼロトラストセキュリティ」
ゼロトラストセキュリティの基本理念は、「すべてを信頼しない(Zero Trust)」という考え方です。これは、社内外のネットワークやパソコンなどのデバイスすべてに脅威を含む可能性があるとみなし、ネットワークインフラや情報セキュリティの強化を実現する方法です。

従来の考え方:
従来は「境界型セキュリティ」と呼ばれ、社内ネットワークは安全とみなしていました。社内のアクセスや会社が管理するデバイスに対しては利便性を考慮し、相対的に低いセキュリティレベルの運用を行っていました。
ゼロトラストの考え方:
「ゼロトラストセキュリティ」では、社内外を問わず全てのアクセスを検証し、信頼性を保証しません。すべてのデバイスや通信をその都度検証し、許可することで、セキュリティレベルを高く保つ考えです。
なぜゼロトラストが必要なのか?
近年のICT(情報通信技術)の急速な進化により、従来の境界型セキュリティが効果を発揮しにくくなっています。その理由は以下の通りです。
- クラウド活用の普及
クラウドサービスの利用が増え、情報の境界が曖昧になってきました。
- テレワークの普及
働く場所が多様化し、社内外の境界が曖昧になっています。
- デバイスの多様化
PC、タブレット、スマートフォンなど、多種多様なデバイスがネットワークに接続されるようになっています。
- 新しいサイバー攻撃手法
標的型攻撃やビジネスメール詐欺など、従来型の境界型セキュリティでは対応できない脅威が増加しています。
ゼロトラストセキュリティで意識すべき6つの脅威
- ユーザーIDのなりすまし:
不正に取得したIDやパスワードを使って正規ユーザーを装った攻撃です。
- データの改ざん
データの偽装または、既存のデータを改ざんする行為です。
- ソースの否認
ログを消去して証拠を隠す、または情報を変更・消去する行為です。
- 情報漏えい
IDやパスワード、個人情報などのデータが流出することです。
- サービスの拒否
サーバーに高い負荷をかけてサービスを妨害する攻撃です。
- 特権の昇格
システムのroot権限などの特権を不正に取得する行為です。
ゼロトラストセキュリティのメリット
ゼロトラストセキュリティの導入によって、以下のようなメリットがあります。
- 柔軟なアクセス管理
権限が許可されれば、どのデバイスや場所からでもアクセスが可能になります。
- セキュリティの強化
常にアクセスを検証し、リスクを最小限に抑えることができます。
- セキュリティポリシーの一貫性
社内外のネットワークに対して同一のセキュリティポリシーを適用できます。
まとめ
ゼロトラストセキュリティは、「すべてを信頼しない」というポリシーに基づき、アクセスリクエストごとに検証を行うことで、セキュリティを強化する考え方です。従来の境界型セキュリティと比較して、より柔軟で強固なセキュリティを提供します。新しい働き方や技術の変化に対応するためには、ゼロトラストセキュリティの理解と適用が重要です。
イシマルでは、サイバーセキュリティの国家資格である情報処理安全確保支援士が在籍し、企業の情報資産を守るためのサポートをしています。インシデントの発生やセキュリティ対策を検討する際には、まずはイシマルへご相談ください。
[執筆]
i365 labo 3rd プロジェクトチーム
(この記事は、2024年10月時点の情報をもとに作成されています。)